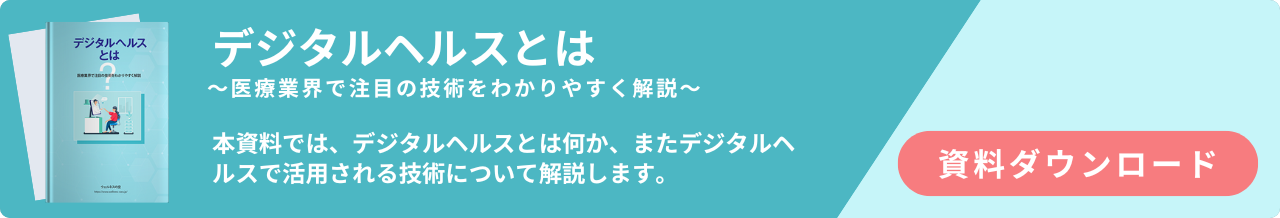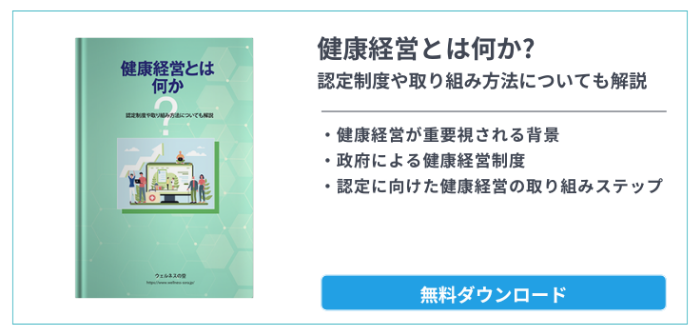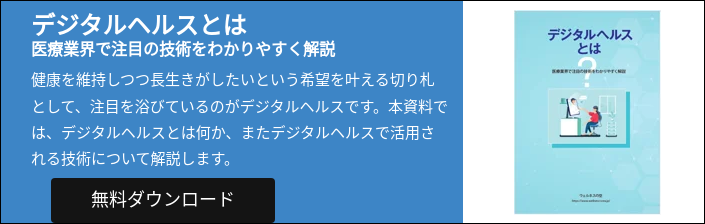人事労務担当者必見! 健康診断の料金は会社負担? どれくらいかかるの?
- 2022.04.28
- 予知・予防
- ウェルネスの空 編集部
入社前と入社後の健康診断は会社と本人のどちらが料金を支払うのか、それぞれの診断にいくらかかるのかなど、経営者や人事労務担当者なら一度は疑問に思った方もいるのではないでしょうか。本記事では、負担者やその相場、必要となる費用を減らす方法まで健康診断にまつわる疑問について解説します。

健康診断の料金は会社負担?
健康診断の実施は会社の義務として定められています。健康診断にかかる料金も、基本的には会社側の負担ですが、入社前や再健診などには個人が負担するケースもあります。
健康診断は会社の義務
会社には従業員に健康診断を受けさせる義務があると労働安全衛生法で決められています。健康診断には、主に雇用の際に行う「雇入れ時健康診断」や1年以内ごとに行う「定期健康診断」があり、その際会社は医師による健康診断を実施する義務があります。また、常時50人以上雇用している事業所では、診断の結果を労働基準監督署に報告し、さらに5年間保管しておかなければなりません。もし会社が実施しなかった場合には法律違反になり、50万円以下の罰金が科されます。
(参照元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057)
入社前の健康診断は会社の義務ですが、健康診断を受けて3ヶ月経たない人材を雇い入れる場合には、診断結果を証明する書類等の提出だけでも問題ありません。
(参照元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032)
入社前の健康診断は、健康上の問題なく業務に従事できることを示す重要なものです。既往歴や自覚症状の有無、胸部エックス線検査、血圧測定、その他血液検査などで、従業員の体調や隠れた病気がないか検査することで、健康を証明します。
1年ごとの定期健康診断は、従業員の疾病の発見や予防、就業できる健康状態かどうか、適正な場所に配置されているかなどの判断を目的として行われます。定期健康診断は勤務時間内に実施時間を設けるのが基本です。実施時期にはとくに決まりがないため、会社側が自由に決められます。
健康診断には、ほかにも、高熱業務や寒冷業務などの特定業務に従事する従業員に対して配置換えのときと6ヶ月以内ごとに実施する「特定業務従事者の健康診断」、海外に6ヶ月以上派遣する従業員が海外への派遣時と帰国後国内で業務に就くときに実施する「海外派遣労働者の健康診断」、事業所の食堂や炊事場で給食業務に従事する従業員が雇用時と配置換えのときに実施する「給食従業員の検便」などがあります。
なお、健康診断は常時雇用の従業員に実施することが法令で定められています。常時雇用の従業員とは以下のいずれかの条件に該当する者を指します。
- 雇用期間に定めがない契約により雇用される
- 雇用期間に定めがある契約だが、更新などにより1年以上雇用されることが決定している、もしくはその予定がある
上記のどちらかを満たした上で、所定労働時間数が正社員の4分の3以上であれば対象となるので、パートタイム従業員やアルバイト従業員に対しても健康診断は実施する必要があります。
(参照:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q16.html)
健康診断にかかる料金は、誰が負担する?
従業員の健康診断は、入社前と定期的にそれぞれ行う必要があります。料金負担は入社前のものと定期健康診断で異なるため、費用の処理に注意が必要です。
1.入社前の健康診断
就職、転職時に従業員が受ける健康診断のことです。従業員の採用時、会社側は従業員に対して入社前に健康診断を受けてもらうか、健康診断を自分で受けて診断結果を証明する書類等を提出してもらわなければなりません。
入社前の健康診断料金については、会社と従業員どちらの負担になるかが法律では規定されていません。ただし、健康診断の実施義務に関する規定があること、安全配慮義務があることなどから、会社側が負担するケースが一般的です。
2.入社後の定期健康診断
入社後の定期健康診断は会社に義務付けられているため、会社が費用を全て負担しなければなりません。受診時間も通常の労働時間として扱う義務はありませんが、受診にかかった時間には賃金を支払うほうが望ましいです。賃金を支払う形ではなく就業時間内に健康診断を行う形を取り入れ、業務の一環としている会社も見受けられます。ただし、後述する特殊健康診断については、所定労働時間内に行うことが義務化されています。そのため、時間外に実施すれば、割増賃金を支払わなければなりません。
パートタイム従業員などの場合には毎日出社しているとは限らないため、健康診断が勤務時間外に行われるケースもあります。勤務時間外に健康診断を受けた従業員に対しては、とくに健診実施時間分の給与支払いまで行うことが推奨されています。
健康診断では、乳がん検診のマンモグラフィーや脳のMRI、胸部CTなど、気になる検査をオプションとして選び、追加で受けることが可能です。けれども、オプション検査は会社に義務付けられていないため、追加費用は従業員負担です。ただし、一部費用負担などを認めている会社もあります。
再検査になった場合の料金負担は?
健康診断の結果は、会社が把握しつつ、従業員へ通知する義務があります。届いた結果に異常がみられた場合再検査が必要ですが、再検査費用は会社負担と規定されていません。そのため、費用負担の対応は会社によりさまざまです。基本的には、再検査料金を個人負担とする会社が多数を占めています。ただし、福利厚生として指定の病院で再検査を受けることを条件に会社負担にするというやり方を取り入れるところも徐々に増えています。
再検査にかかる時間に対しても賃金を支払う必要もありません。ただし、会社は従業員に対して安全配慮義務が課されているため、従業員が再検査を受診しやすい環境を作ることが大切です。
会社が負担する健康診断の料金相場
一般健康診断は「雇入れ時健康診断」や「定期健康診断」などが、特殊健康診断では「放射線業務健康診断」、「じん肺健康診断」などが会社に義務付けられ、それぞれ料金の負担が発生する健康診断です。健康診断は自由診療なので料金は病院によって異なり、一般健康診断の値段の相場は、7,000〜10,000円/人ほどです。「雇入れ時健康診断」と「定期健康診断」では定められている診断項目はほとんど同じですが、雇入れ時健康診断では「胸部エックス線検査及び喀痰検査」の「喀痰検査」を受ける必要がないなど、わずかな違いがあります。
定められた業務や特定物質を取り扱う作業を行う従業員に必要な健康診断が特殊健康診断です。そのうちの一つである、放射線業務に従事する従業員に対して実施される「電離放射線健康診断」では、3,000〜6,000円/人ほどで、電離放射線の影響が現れていないか検査します。
また、「じん肺健康診断」は、粉じん作業を行っている従業員に必要な健康診断です。検査料は約4,000円/人で、粉じんが原因で肺や呼吸器官に異常が生じていないか検査します。
【一般健康診断】11項目:7,000〜10,000円/人
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(蛋白及び糖)
- 心電図検査
※雇入れ時健康診断では、4は「胸部エックス線検査」のみ
【特殊健康診断】
- 電離放射線健康診断(問診、診察、血液検査(赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血液像)) 3,000~6,000円/人
- じん肺健康診断(問診、診察、エックス線検査、胸部に関する臨床検査、肺機能検査、動脈血ガス分析検査) 約4,000円/人
少しでも負担額を抑える方法は?
健康診断にかかる会社の費用負担を抑えるためには、健康診断の料金を安く設定している病院を選ぶことが大切です。病院を選ぶ際には、必ず料金を比較検討しましょう。
パートタイム従業員やアルバイト従業員が個々に国民健康保険に加入しているようなら、それを利用して年に一回の無料健康診断を受けてもらえば、費用負担の軽減が可能です。大学生の場合は健康診断に学割が適用になるケースもあり、1,000〜2,000円ほど安く受診できます。
雇入れ時健康診断を個人負担で行うことも負担額の軽減につながりますが、この場合、その旨を募集要項などで早めに案内しておきましょう。
まとめ
会社が実施する健康診断は、従業員の健康を守るために行うものです。従業員への安全配慮義務もあり、実施しないと会社が罰金を科せられるため、入社時と毎年1回の定期健康診断は行う必要があります。
入社後の健康診断は会社負担で行いますが、入社前の健康診断については会社の費用負担が定められていません。入社前の健康診断を従業員の負担にする場合には、後々混乱させないように早めに伝えておきましょう。健康診断は自由診療です。保険が適用されないため高額になりがちですが、少しでも負担額を抑えたいなら、料金設定が低い病院を探すなど、できる対策をとりましょう。
この著者の最新の記事
-

- 2025.02.21
- 健康維持・増進
健康づくりのきっかけになる「特定保健指導」とは?必...
-

- 2025.02.19
- 健康維持・増進
ウェルネスにおけるサプリメントを解説 従業員の健康...
-

- 2025.02.14
- 診断・治療
医薬品の流通管理|現状や課題、解決方法について解説
-

- 2025.02.10
- 診断・治療
くすり相談窓口:医薬品の適正使用を支える重要な存在

この記事が気に入ったら
いいねしよう!